この記事の内容

「とりあえずServiceNow導入」で現場が混乱…ITサービス運用責任者が直面した失敗とは?本記事では、老朽化システムに悩む企業がITSM導入で陥った“あるある”失敗を読み物形式で紐解き、再起へのロードマップを解説します。
毎朝、未処理チケットの山を前に溜息をつく…。
老朽化したシステムとサイロ化した運用体制、そして慢性的な残業。
そんな現状を一変させる起爆剤として、白羽の矢を立てたのがServiceNowだった。「これを入れれば、業務は自動化され、残業も減るだろう」
たしかに、ServiceNowはITSM(ITサービスマネジメント)領域で世界的に高い評価を受けており、可視化・標準化・自動化を一気通貫で実現するプラットフォームとして注目されていた。だが、その期待は、現場の混乱と不満へと急転することになる。
「とりあえず導入」で現場が混乱…目的なきシステム刷新の代償
“最新ITSMツールの導入”を急ぐあまり、本来最も重要だった問いを見失っていた。
「何を解決したいのか?」
当時、IT運用グループが抱えていたのは以下のような課題だった。
• 老朽化した資産管理システムが属人化しており、情報が分散
• インシデント処理に平均72時間、重大障害では1週間以上
• 各部門で異なるツール・手法が混在し、連携が成立していない
• 月末には平均30時間以上の残業が常態化
これらの“構造課題”を解きほぐすことなく、ツール先行でServiceNow導入を進めた結果…
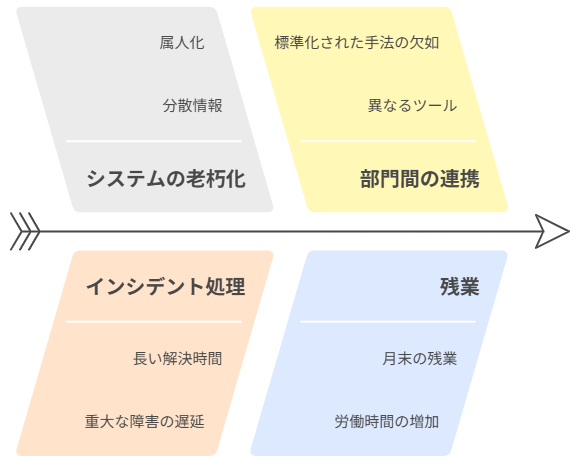
事例1:要件の曖昧さが招いたユーザー不満
現場の声を拾わずに作成した要件定義書は抽象的で、「今の運用に合わせておけばいいだろう」という安易な判断が横行していた。
導入後に、このような不満が相次いてしまった。
• 「どの画面から何をすればいいかわからない」
• 「ワークフローが現場と合っておらず、結局Excelに逆戻り」
• 「承認プロセスが複雑化し、対応がさらに遅延」
現場の混乱は、CSAT(顧客満足度)にも影響し、スコアは1四半期で18%低下。MTTR(平均復旧時間)は短縮どころか、むしろ悪化した。
事例2:標準化の失敗とサイロ化の再発
さらに致命的だったのが、「部門ごとに異なる要望をすべて受け入れてしまったこと」だった。
業務プロセスの可視化も行わないまま、各部署の「現行維持」を優先した結果──
• 部門間で承認ルートやチケット分類がバラバラ
• レポート基盤が統一されず、横断的な分析が不能
• 利用状況に差が生じ、定着率に深刻なばらつき
つまり、“ServiceNowという先進ツール”が、むしろ混乱の温床となってしまったのだ。
これは、「導入が目的化する」という古典的なミスを犯していた証左だった。
事例から浮き彫りになった2つの教訓
“最先端”や“世界標準”という言葉に踊らされ、本来向き合うべき相手…「現場の課題」と「運用の実情」から目を背けていた。
そこで導入失敗を機に、以下の2点に注力することに決めた。
1. システム導入の目的を明文化する
・インシデント対応にかかる平均時間を72h→24hに短縮
・月間30hの残業を20h以内に抑制
2. 現場主導で課題の棚卸しを行う
・「何に困っているのか」を、ユーザー目線で可視化
・要望の中に“既存文化”を維持したい心理がないかも確認
上記2点に注力し、ServiceNow導入を「ツールの話」ではなく、「課題解決の一環」として捉え直した。
そしていきなり全社導入ではない、ある部署だけのスモールスタートから始めることで、スムーズな導入を実現できる。
FAQ
Q1:導入がうまくいかない理由は何でしょうか。
A1:明確な目的や現場の課題を整理せず「最新ツールの導入」自体が目的化しているためです。
結果、要件が曖昧で、システムを使いこなせない形となります。
Q2:スムーズに導入させるコツは何でしょうか。
A2:現場主導で課題の棚卸しと目的の明文化を行い、スモールスタートとITILベースの標準化を徹底するのがベターです。
Q3:スモールスタートのメリットは?
A3:リスクを抑えながら成功体験を得られる点です。段階的に拡張することで現場の混乱を最小限に抑えられます。
また導入までの期間を短縮し、コストも抑えられます。
Q4:導入効果をどのように測定するのでしょうか。
A4:MTTRやチケット対応率、定着率など定量指標を導入前後で比較すると良いと思います。
まとめ
ServiceNowの導入失敗を通じて、大きな教訓を得たこと、それは「ツールが解決するのではない。課題に向き合う姿勢とプロセスの整理こそが成否を分ける」ということ。
もしあなたの現場でも、下記の状態であればすぐに対応が必要です。
• インシデント対応に丸1日以上かかっている
• チーム間で情報連携が成立していない
• システムが老朽化し、改修コストだけが膨れ上がっている
ServiceNowの“多機能さ”や“柔軟性”が、プロジェクトを迷走させることもあります。
だからこそ、「小さく始めて、大きく育てる」という戦略が鍵になるのです。
そこで、オススメする再挑戦のステップは、次の通りです。
導入を失敗させないためのロードマップ
1. 課題の棚卸し
・現場主導でボトルネックを抽出し、影響度を分類
2. 目的の明確化
・何を、どれだけ、いつまでに改善したいかを定量化
3. スモールスタート
・影響範囲の限定された部署から段階的に導入
4. 標準化と内製化
・ITILベースでプロセス設計、UIは現場と連携して調整
5. 定着支援と評価指標の設計
・トレーニングと定量評価(MTTR、定着率など)で改善循環
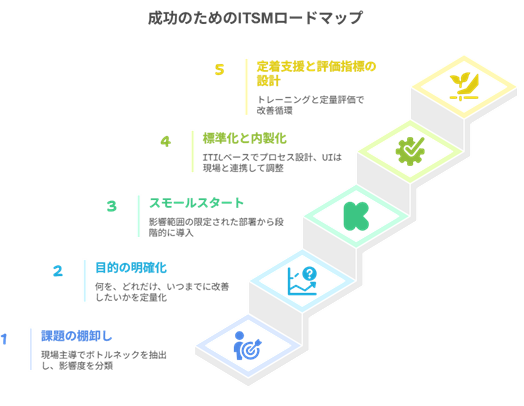
「IT部門が変われば、全社の生産性が変わる」その実感を数字で証明できることでしょう。
最短ルートでITSM導入を成功させるために、まずは下記資料で、ServiceNow導入の正しい設計図を確認してみてください。




 資料ダウンロード
資料ダウンロード